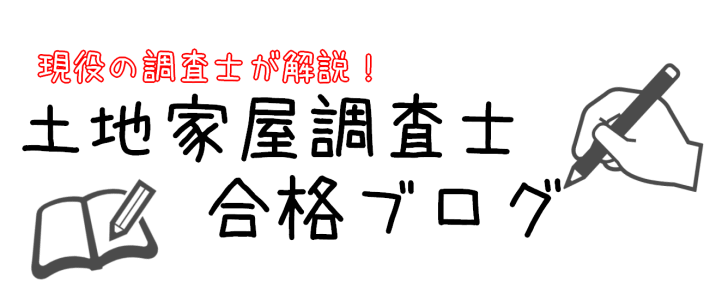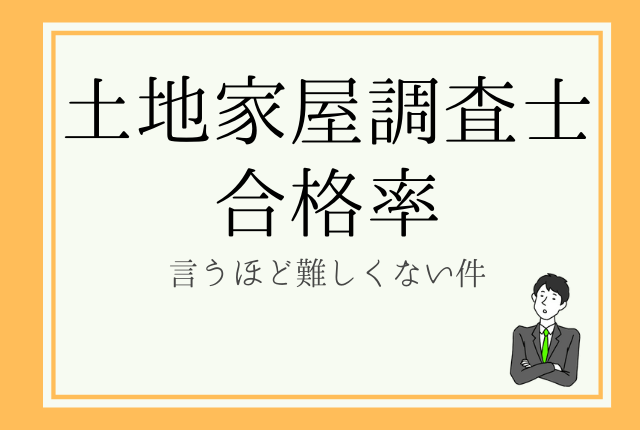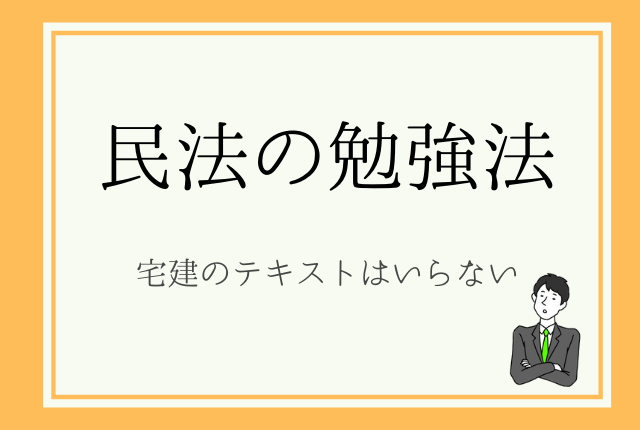

独学で勉強してるんだけど民法ってどうやって勉強すればいいの?
やり方がイマイチ分かんないんだよな~
土地家屋調査士試験に対応してるテキストってほとんど売ってないよね?
そんな疑問にお答えします。
土地家屋調査士試験では1問目から3問目に民法の問題が出題されます。
全て正解ならば7.5点もGETできます。
択一式は足切りがあるのでせめて2問は正解しておきたいところです。
参考:【土地家屋調査士試験】択一で逃げ切れ!合格できるベストな配点を経験者が解説
ですが、民法の勉強法ってイマイチ分からないと思いませんか?
予備校に行っている人ならば、講義で使用しているテキストを読めば良いと思いますが、それ以外の人はどうすればいいんでしょう?
この記事で分かること
- 土地家屋調査士試験に出題される民法の範囲
- 民法の具体的な勉強方法
- オススメのテキスト(一冊でOK)とスマホのアプリ(無料)

というわけで、独学で一発合格した現役の調査士が解説します。
参考:【土地家屋調査士】半年の独学で合格した勉強方法&スケジュール
ここに紹介しているものしかやってないですが、択一の得点は45点でした。
民法の勉強方法で迷っている人は参考にしてくださいね!
こちらの記事は動画で見ることができます。
土地家屋調査士試験、民法はどうやって勉強する?

宅建の民法について
独学の場合は宅建のテキストで学習をすればいいと言われることがあります。
宅建の試験で出題される分野のひとつに「権利関係」があるのですが、これが調査士試験で言う「民法」です。
私は宅建の資格も保有していますが、権利関係の範囲を全て暗記するのはあまりオススメしません。理由は両者では試験範囲が違うからです。
簡単に言えば、宅建のテキストを買って権利関係の部分を全て暗記をするというのはとても非効率ってことです。
宅建のテキストを使う場合には、調査士試験でも出題される範囲だけを勉強すれば良いのです。
注意点ですが、民法は令和2年度に法改正が施行されます。
改正前のテキストでは解答が異なるので気を付けてくださいね。
参考:【経験者が解説】土地家屋調査士試験と宅建の難易度を徹底比較してみた
どこを勉強すればいい?
出るところだけやればいいとは言っても、調査士試験を初めて受ける人にとっては一体どこを勉強すれば良いのか分からないですよね。
ということで、過去の出題範囲を見てみましょう。
・総則(計16問)
自然人・・・・・・・2問
物・・・・・・・・・・・1問
意思表示・・・・・4問
代理・・・・・・・・・3問
無効・取消し・・1問
条件・期限・・・・2問
時効・・・・・・・・・3問
・物権(計18問)
物権総論・・・・・1問
物権変動・・・・・7問
占有権・・・・・・・2問
所有権・・・・・・・6問
用益物権・・・・・1問
・債権(計0問)
・家族法(計5問)
相続法・・・・・・・5問
物権変動や所有権の問題は頻出です。不動産売買と関係がある論点だからですね。
あとは代理や相続もよく見ますね。これも土地家屋調査士の仕事に関係があるからだと思います。
オススメの基本テキスト
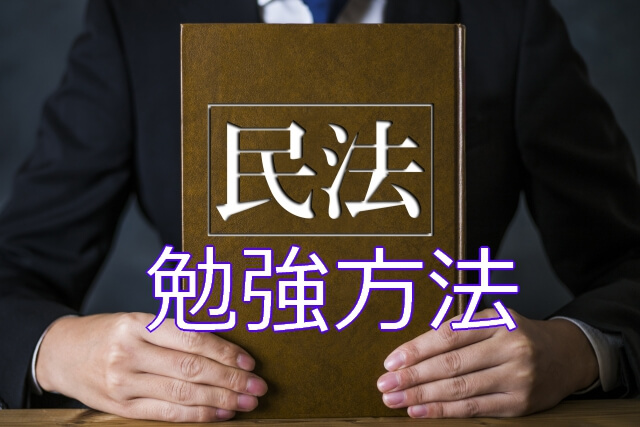
ここからは私がオススメする勉強方法を紹介します。
宅建のテキストを使ってもいいですが、もっと効率よく学習できる方法があります。
マンガでわかる民法入門
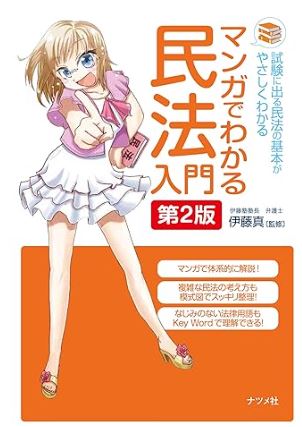
民法を全く知らないという人はいきなり過去問を解いても内容が理解できないと思います。
初心者にオススメなのは「マンガでわかる民法入門」です。漫画なのでサクッと読めますし、かなりとっつきやすいです。
手順は下記の通り。
- 出題範囲を上記のテキストで読む
- ある程度理解できるようになったら、調査士試験の過去問を解いてみる(1~3問目だけでOK)
- 分からない部分があったらテキストを見直す
最初はほとんど解けないと思いますが、民法の問題は何度も繰り返していく内にスピーディーに解けるようになるし、簡単に思えるようになるので大丈夫です。
行き詰った時にはテキストを読み直して理解を深めます。
テキスト→過去問→テキスト→過去問と繰り返して行えば、1か月ほどで調査士試験の民法程度なら7割くらいはマスターできると思います。
ちなみに、テキストでなくてもYouTubeなどで民法初心者向けの動画を見てもOKです。お金をかけたくない人は「民法 初心者」などのワードで検索して探してみてください。
土地家屋調査士受験100講〔II〕理論編 民法とその判例(早稲田法科専門学院)
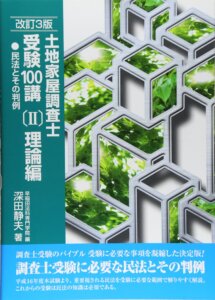
試験用のテキストでは「土地家屋調査士受験100講〔II〕理論編 民法とその判例」があります。
試験で必要な知識のみがまとめられていますが、かなりボリュームがあり解説が難しいです。
一読するだけでもかなり時間がかかるので、個人的には試験に出題される分野を「マンガでわかる民法入門」で学習して、さっさと過去問を解いたほうがいいと思います。
民法を丸ごと捨てるのはNGですが、不動産登記法のほうが圧倒的に大事なので、ここで時間をかけるのはもったいないです。
土地家屋調査士 択一攻略要点整理ノート Ⅰ・Ⅱ(東京法経学院)
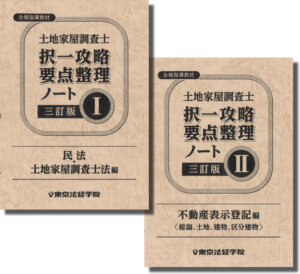
東京法経学院からも試験用のテキストが販売されています。こちらのテキストもボリュームがあります。
ちなみにこのテキストはセット売りになっています。
- 民法・調査士法
- 不動産表示登記
民法編だけ買う…ということはできないので注意。
テキストの内容は下記の通り。
- 基本的な解説
- 関連する判例の紹介
- 練習問題
- 練習問題の解説
1分野終わったらすぐに練習問題を解けるような仕組みになっているので、インプット後のアウトプットがスムーズです。
「テキスト読んだだけで理解した気になる」・・・というパターンが起こりにくいですね。
個人的には、早稲田法科専門学院のテキストよりも東京法経学院のテキストのほうが好きですね。
注意点ですが、東京法経学院の過去問と同様でこのテキストも書店で販売されていません。東京法経学院の実際の校舎か、公式サイトで購入する必要があります。
※人気のテキストのため、品切れになる場合があるので注意です!
どのテキストを選ぶべき?
個人的には「マンガでわかる民法入門」で基礎学習をしてすぐに過去問を解くことをオススメします。
もっと知識を深めたい部分がある場合のみ、早稲田法科専門学院か東京法経学院のテキストを読み込めばいいです。
ただし、難くても詳細なテキストを読みたい人は、序盤から早稲田法科専門学院か東京法経学院のテキストを使ってもいいです。このあたりは好みでOKです。
ちなみに私の妻はこれらのテキストは買っていませんが、択一で満点をとっています。なので、過去問と実践答練のみでも合格は可能です。
オススメの過去問
基本的な知識をインプットしたら、出来るだけ早く過去問にとりかかりましょう。
調査士試験はアウトプットの勉強のほうが大事です。ここではオススメの過去問をご紹介します。
土地家屋調査士 択一過去問マスターⅠ(東京法経学院)
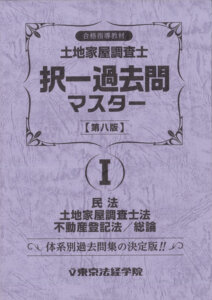
東京法経学院が販売している過去問です。こちらのシリーズはⅠとⅡがあるのですが、民法が収録されているのはⅠのほうです。
Ⅰに掲載されている問題は全部で299問です。平成元年度~令和2年度の問題&昭和年代の重要問題はセレクトして収録されています。
ちなみに東京法経学院には「新・合格データベース」という問題集もあります。
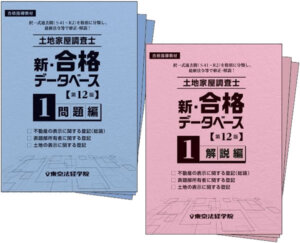
「択一過去問マスターⅠ・Ⅱ」との大きな違いは掲載されている問題の数と金額です。
| 名称 | 問題数 | 金額 |
|---|---|---|
| 択一過去問マスターⅠ・Ⅱ | 553問 | 12,870円 |
| 新・合格データベース | 3,312問 | 27,500円 |
新・合格データベースは昭和41年度から令和2年度までの問題が掲載されているため、問題数がかなり多いです。
3,312問というとかなりボリュームがあるので、一周するだけでも時間がかかります。調査士試験は択一式だけでなく記述式の問題もあるため、択一式に時間をかけすぎるのはあまりオススメしません。
「択一過去問マスター」のほうが、ボリューム感がちょうどいいので、個人的には一番オススメの過去問題集です。
実際の校舎か公式サイトで購入できます。いずれⅡも必要になるので、こちらを買うならⅠとⅡを両方買った方がいいですよ。
土地家屋調査士 択一式過去問(日建学院)
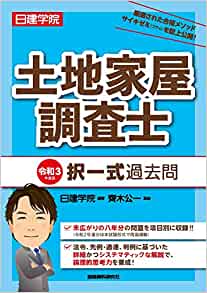
日建学院の問題集はAmazonや書店で購入できます。私はこちらを使っていました。
8年分の過去問が分野別に載っているため、それぞれの項目ごとの勉強ができます。解説が分かりやすく、初心者でもとっつきやすいですが、東京法経学院の過去問に比べてボリュームが少ないです。
なので、この過去問を使う場合は実践答練や模試などを使って演習量を増やしたほうがいいです。
私が受験生時代には東京法経学院の問題集が売っていなかったので、この過去問を使っていましたが、これから勉強する人は東京法経学院のものを使うことをオススメします。
ただ、書店などで手に入りやすく値段も手ごろなので、とりあえず試験のレベルを知りたいという人は買ってみてもOKです。
ハイレベルな問題を解きたい場合
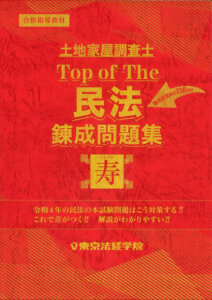
もっと難しい問題を解きたいという人は東京法経学院の「土地家屋調査士 Top of The 民法 錬成問題集【寿】」という問題集をオススメします。
こちらの問題集は民法対策として難易度が高めの問題が収録されています。
過去に東京法経学院の司法書士答練などで出題した民法の問題群を、土地家屋調査士の民法対策用に編集したものになります。
択一式と記述式の問題が一通り終わった後に余力があったらやってもOKです。
その他の勉強方法
宅建 過去問 (スマホアプリ)

出先で問題を解きたいなら、「宅建 過去問」というスマホのアプリがオススメです。
私も受験生時代に使っていました。iPhone、androidのどちらにも対応しています。
出題が分野ごとに分かれているので必要な部分だけを解くことができます。
また、間違えた部分のみを出題することもできるので効率よく学習を進めることができます。

テキストを電子書籍化する(自炊)
択一の勉強は隙間時間を有効に使って行うのが効率が良いです。
ですが、常にテキストを持ち歩くのは重いし、邪魔ですよね。
なので私は、紙のテキストをタブレットやスマホの端末で読めるようにして、外出時でも気軽に勉強できるようにしていました。
詳しくは動画にまとめているのでよかったらどうぞ。
予備校を使うのもオススメ
自分で学習するのが苦手な人は迷わず予備校を利用しましょう。サクッと勉強することができます。
調査士試験は民法以外にも覚えることがたくさんあるので、民法だけに時間をかけるのはかなり非効率です。
予備校を使う場合は、民法以外の択一の勉強もまとめて行えます。
独学よりも圧倒的に楽なので、個人的には予備校の利用をオススメします。
調査士試験に対応している予備校は全部で5校あります。
価格や講座の内容について知りたい人はこちらで詳しくまとめています。
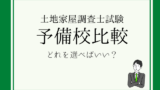
独学での択一式の勉強方法についてはこちらでまとめています。