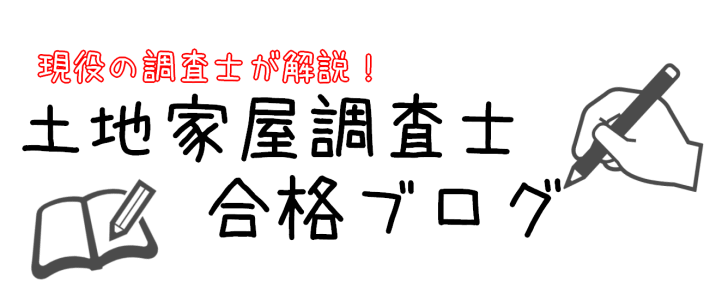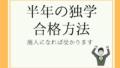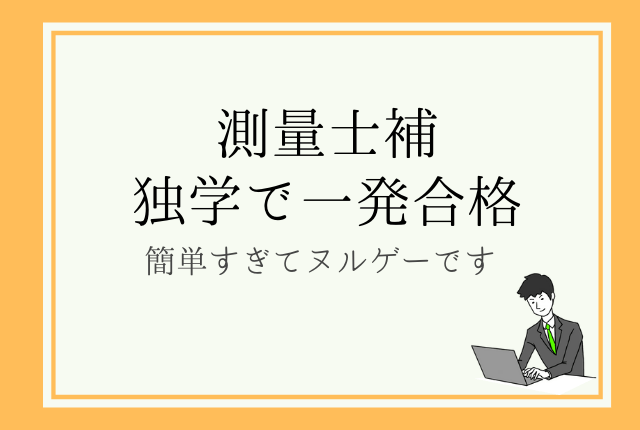

測量士補って簡単って言われてるけど本当にそうなの?
どれくらい勉強すればいいのかな?
てか測量士補をとれば転職に有利なの?
そんな疑問にお答えします。
測量士補試験は土地家屋調査士試験の午前の部の免除のために受験する人も多いですよね。
ほとんどの人が測量士補→土地家屋調査士というステップを踏むと思います。
ちなみに私も測量士補を取得した年に土地家屋調査士にも受かっています。(どちらも一発合格です)
また、測量士を受験する前段階として測量士補を受験する人も多いです。
正直なところ、この試験はかなり難易度が低いです。普通に勉強すれば誰でも受かります。
ですので、測量士補に合格すれば就職が有利になる・・・ということはほとんどありません。
キャリアアップを狙うなら測量士補ではなく測量士を目指しましょう。
今回の記事では私が測量士補に合格した方法と測量士補と測量士の違いについて解説していきます。
この記事で分かること
- 測量士補試験に最短で受かる勉強方法
- キャリアアップを狙うなら測量士を取得するべき理由
- 測量士試験に対応した資格予備校の特徴
測量士補の勉強方法のみ動画で見ることができます。
過去の合格率を確認しよう
「未経験で測量の知識なんて全くないけど大丈夫?」と思う方もいると思います。
大丈夫です。私も測量のことなんて全く勉強をしたことがない素人でした。
測量士補試験は難易度がそれほど高くないので基礎的なことをしっかり覚えていけば余裕で受かります。
過去の合格率はこちら。
| 形式 | 出題数 | 配点 | 合格基準 |
| 択一式 | 28問(1問25点) | 700点 | 450点以上 |
| 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | |
| 合格率 | 21.40% | 40.70% | 21.20% | 39.70% | 28% | 35.90% | 47.30% | 33.60% | 35.80% | 30.30% | 34.80% |
合格率だけをみれば難しく感じるかもしれませんが、そんなことはありません。
そもそも問題自体が易しいのですが、この試験は28問中10問を間違えても受かります。受験年度の難易度が高くても低くても合格基準点は変わりません。
資格試験の中では攻略が簡単なので、合格しやすい部類に入ります。
「オレは勉強したのに落ちたんだけど!?」という人は勉強方法を変えた方がいいですね。地頭が悪いというより、勉強効率が悪いのだと思います。
ちなみに女性の受験者も数名いました。
男性ばかりで受けにくいなぁと感じるかもしれませんが、最近では女性の測量士や土地家屋調査士が増えているようなのであまり気にしなくても良いと思います。
とりあえず問題を見てみたいという人は国土地理院のサイトに載っているので開いて見てください。
合格のための勉強時間は?一夜漬けでも大丈夫?
まず気になるのは勉強時間ですよね。
世間では簡単とは言われているけれど実際のところどうなの?と思う人もいるでしょう。
結論から言うと1か月みっちり勉強すれば受かります。2か月前から勉強を始めれば余裕で受かります。3か月前から始めれば最後には暇になります。
一般的には、2か月前くらいから勉強を始める人が多いようです。
私の同僚には全く勉強しないで合格した人もいますが、かなり運任せなので最低でも1か月は勉強したほうがいいです。もちろん、一夜漬けでも厳しいです。
1日の勉強時間は2時間程度で良いと思います。仕事の合間にテキストを少し読んだりするなら帰宅後の勉強時間は1時間程度でもいいかもしれません。
多忙でないなら、働きながら取得することも可能です。
スケジュールはどんな感じ?
では実際に測量士補を受験した私のスケジュールをご紹介します。
- 1月 受験申込
- 4月上旬 勉強開始(基本テキストを読むが、時間的余裕がなく挫ける)
- 4月中旬 動画を見始める
- 4月下旬 過去問スタート
- 5月 過去問と動画勉強を繰り返す(試験前に勉強に飽きるw)
- 5月20日 試験日
※近年はコロナの影響で試験日時が違うので注意してください。
参考:国土地理院
1か月で測量士補に受かる勉強方法
ステップ1:動画で勉強する
最初はテキストを読んでいたのですが、未経験の初心者のせいかイメージがつきにくく挫折しそうになりました。内容が全く頭に入ってこないのです。
どうしようかなぁ~と悩んでいたところ、偶然にもYoutubeで測量士補の解説動画を見つけました。
テキストをダラダラと読むよりも、この動画を見て過去問を解いた方が断然早いです。
とても分かりやすいですし、内容もコンパクトになっているので最短での合格が可能です。
とりあえず、先ほどのチャンネル内にある「基礎知識まとめ」というプレイリストを全て再生して内容を8割くらい理解できたらOKです。
その時点で過去問を解いてもある程度解けるようになっています。大体2週間内で見終われば良いと思います。
ちなみに測量士補試験では
- 基準点測量
- 水準測量
- 地形測量
- 地図編集
- 写真測量
- 応用測量
という6分野に分かれていますが好きなものから動画を見て良いです。
テキストでは上記のような順番で書いてあるし、過去問もこの順番で出されることが多いですがあまり気にしなくても良いと思います。
不安なら基準点測量→水準測量→地形測量まではこの順番でやって、他の3つはあまり他のジャンルと関連がないので好きなように学習を進めればいいです。
注意点ですが、数学が苦手な人は公式を覚えながら進めましょう。
詳細はこちら。
ステップ2:必要なテキストを準備しよう
測量士補 過去問280(日建学院)
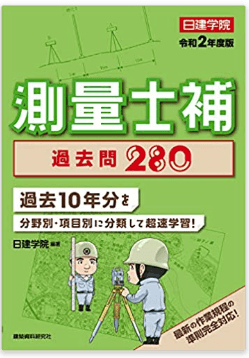
動画である程度の知識がついたら実際に過去問を解きます。私はこちらの過去問を解いていました。10年分の過去問が項目別に載っています。
測量士補の出題傾向はそこまで大きく変わるわけではないので、この過去問を全てマスターできれば普通に受かります。
過去問の解説を見ても分からない箇所が出てきたら動画で確認します。最終的に過去問が全て完璧になればOKです。
計算問題はある程度慣れてきたら電卓を使ってもいいです。計算式だけ書いておいて、解説と見比べる感じですね。
他に問題を解かなくてもいいのか?と心配になると思いますが大丈夫です。過去問が全て解けるなら試験には受かります。模試もいりません。
補足:建築土木教科書 測量士補 合格ガイドは買わなくていい
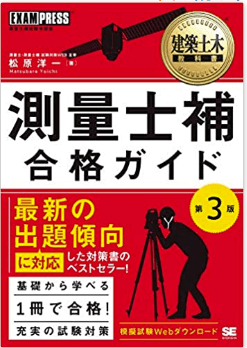
Amazonで測量士補のテキストを検索すると真っ先に出てくるテキストです。このテキストはかなり丁寧な内容になっているのですが、逆に言えばボリュームがありすぎる。
私も最初から頑張って読んでいたのですが専門用語が多いし、未経験のせいか現場作業のイメージがつきにくくて内容が理解できませんでした。
この本を読むよりは先ほど紹介した動画を見た方が時間的にも知識的にも有利です。
一応買っても良いとは思いますが、わざわざ購入しなくても合格はできます。私のように最初から読もうとするのはオススメしません。時間のムダです。
【知識の補強】測量士&測量士補試験対策WEB
測量士や測量士補を受験する人ならほとんどの人が知っているサイトです。過去問や解説が詳しく載っているので非常に役に立ちます。
こちらのサイトにある「WEB〇×テスト」をスキマ時間などにやりましょう。知識の補強に最適です。
測量士補の勉強方法まとめ
- だいたい二か月前から始めればOK
- 動画→過去問→動画→過去問で勉強を進めて過去問を完璧にする
という感じです。試験では数学で習った三角関数の知識が必要なのですが、私は三角関数を完全に忘れていたので1か月の勉強が必要でした。
動画を繰り返し見て過去問を解けば普通に合格できます。おそらくこの方法が一番簡単で最短です。
さて、ここまでは測量士補の勉強方法です。この先は測量士について解説していきます。
測量士補と測量士の違いは?
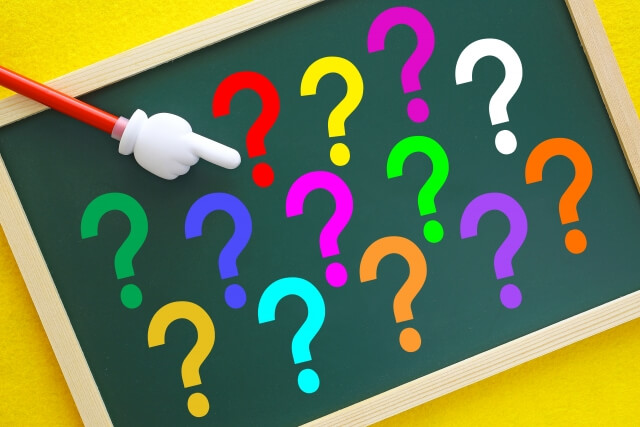
測量士補の上位の資格として「測量士」があります。測量士補も測量士も試験日は同じです。
これら2つの大きな違いは独立開業ができるかどうかです。
正直なところ、測量士補を取得するのは「学校のカリキュラムにあるから」または「土地家屋調査士試験の午前の部が免除になるから」・・・という理由がほとんどです。
測量士補は誰でも取れるので特別な評価はされません。ハッキリ言えば、就職やキャリアアップが目的なら測量士補を取得する意味はあまりありません。
ですので、将来性を考えるなら測量士補ではなく測量士をとったほうがいいです。
※測量士補を取得して自信をつけたい人や、測量士補→測量士の流れで取得を目指す人は別です。
両者の違いを詳しく知りたい人はこちらをどうぞ。
参考:測量士と測量士補の違いは?《仕事内容・難易度・勉強方法》
注意点ですが、測量士補よりも測量士のほうがはるかに難しいです。しかも、測量士は試験対策用の分かりやすいテキストが市販されておらず、ネットで調べてもあまり情報がないので独学での対策がしにくいです。
測量士は独学で合格は無理?
測量士の独学が完全に不可能なわけではなく、未経験からの独学でも一発合格する人はたまにいます。ただし、計算問題がかなり難しいので要注意です。
具体的な勉強方法は下記の記事を参考にしてください。詳しく解説しています。
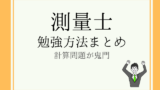
とういうわけで下記に該当する人は資格予備校を使って勉強をしましょう。
測量士試験の勉強で予備校を使うべき人
- 2~3か月の勉強期間で合格を狙う人
- 数学が苦手な人
- 測量士補試験にまぐれで合格した人
- 測量士補の計算でつまづいた人
- 専門的なテキストを読むのが苦手な人
- 測量に関する知識がない人
測量士の通信講座はアガルートアカデミーがオススメ

2021年に「アガルートアカデミー」から測量士試験に対応した講座が開講されました。詳細は下記の通り。
合格総合講義(アガルートアカデミー)
- スマホ・タブレット・パソコンから視聴する
- 倍速機能がある
- 質問制度で講師に何度も質問できる
- 動画は一本5分程度。スキマ時間を使って勉強できる
- テキストがフルカラーで見やすい
- 全額返金制度あり(合格すれば受講費用が返金される。※条件あり)
- お祝い金制度あり(30,000円)
【講座の料金】
- 合格総合講義:162,800円
- 合格総合講義+定期カウンセリング:272,800円
※定期カウンセリング=月1回の講師によるヒアリングです。
こちらの動画で講座の内容を詳しく紹介しています。
動画:【測量士試験】合格総合講義 基線ベクトル サンプル講義 中山祐介講師
アガルートアカデミーの公式サイトではサンプルテキストや動画が確認できるので、気になる人は見て下さい。
今回の記事はここまでです。